 生きている時の姿
生きている時の姿  生きている時の姿
生きている時の姿 |
|
貝というのは 海の底に 生きる生物だけあり、形のない 不思議な 軟体生物です。殻があるから 初めて「 貝だ! 」と 認識できると言って 過言じゃないですね。 生息地も様々。水深 1mから 300mの 泥の中、砂地、珊瑚の上に 住みます。 以下の写真でも おわかりの通り、実に ユニークな形をしており 体の色 (外套膜) も 赤 ・ 黒 ・ 茶 ・ 白 など 実に 多彩。 足の形状も 個々に違うようです。 (写真参照) ダイビングをする方であれば 目にしたことが あるかもしれませんね。 大抵の場合、肉眼では 滅多に お目にかかれない姿だと 思います。タカラガイなどは、外敵が おらず 緊迫していない時は 外套膜で 殻全体が 覆われている姿で 海底に いたりしますので、まさに その姿は エイリアンのようです。 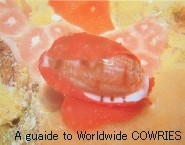 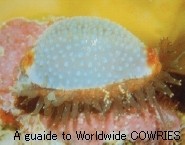
|
 貝の採取地
貝の採取地 |
|
貝が 良く採れる海。一概には 決め難いですが フィリピンが最有力でしょうか。 貝の卵が 孵化すると 貝の 子供は海流に 乗り あちこちに 流れて行きます。 気ままな海流の旅を 終えると、後は 静かに その場所で 一生を過ごします。 ( 大抵は 途中で 採取されてしまったり、食べられたりして 天寿を まっとう出来なそうですが ・ 笑) どこで 潮の流れを下車するのか、そこに 降りるのは 偶然なのか 意思なのか。 貝の発掘地を見て、ふと 思うことです。 同じ種類の貝でも 採取地が違えば 殻色の濃い薄い、模様の 黒化 や 白化など 環境や 食糧事情により 異なることもあり 見分けが 難しいものもあります。 標本貝として 傷欠けなく 完璧な貝殻というのは 稀なのかも 知れないですね。 私のコレクションで 最も 多い 採取地はフィリピンです。 全ジャンル含め、この国で採取されたものが大多数を占めています。 次いで オーストラリアや フロリダなどが上げられます。聞くところによれば フィリピンの 貝漁師さんは 実に 手先が器用で 中には 死貝の殻に 本物同様の 細工を施し、業者や 観光客の方には 本物と称して 販売する方もいるのだそうです。 そんな方ばかりではないでしょうが、旅行先で 標本貝を 買われる方は、偽物を 掴まされないよう 充分 お気をつけください。 また 種類により、温水を好む貝、逆に冷水を好む貝と 存在します。 帆立貝などは 冷たい海水でないと 死んでしまうので 高い海水温の 海には 当然いません。 そのため、外国でしか 産出されない貝というのも 当然あります。それが 何故だか 日本の浜辺に 打ちあがっていることが、稀に あるようです。 奇跡的に 日本の海に 流れてきて 打ち上げられたのだろうか? 実に、低い可能性です。 最も 考えられることとして 手元にある 標本貝を 誰かが 日本の海に 捨てたということになります。 確かに 元は 海にあったものですが、浜辺に捨てるというのは 感心できません。何かしらの事情で 廃棄する際は、自治体の ルールに沿って 廃棄することを お勧めします。先に触れたように、貝ごとに 好む生息地は 異なる点からも、明らかに 海外で しか 採取されない種類のものが、日本の海で 採取される確率は ゼロに 等しいことでもあります。 |
 生貝と死貝
生貝と死貝 |
|
タイトル通り、生貝と死貝の話です。当ページでも 死貝の掲載が 何点かあります。(和名の横に◆マークがついています。) 実際に 標本用の貝として 売られているのは いわゆる、生きたものを採取して 中身を出した貝殻になります。 稀に 死んだ貝を 販売する事もありますが、その際は 「 死殻 」 という 表記をされているのが 一般的です。 タカラガイで 説明するならば、生きた貝殻 (生捕り) ですと、殻が ツヤツヤと 輝き ガラス細工のような 光沢があります。 これが タカラガイの持つ独特の特徴であり 魅力だったりするのですが ( たまに違う種類もありますが ) 死貝 (死殻) になってしまうと、この 艶がなくなり 貝の表面が くすんだようになってしまいます。 中身のなくなった殻は 海中を 波で転がされ、岩や砂の摩擦で 時間が経つにつれて 艶が消え、浜に打ち上げられる頃は すっかり くすんでしまうのです。 海で 貝拾いをし 波打ち際に 転がっているタカラガイを拾うと 水に濡れている時はツヤツヤ光っているのに 家に帰って 見たら 光ってなかった。こんな経験をした人も いるかと思いますが、その理由がこれです。生きているからこそ 保てる艶なんですね。 貝の採取地の話で、フィリピンの漁師さんが 死んだ貝殻に細工を施す。というようなことに 触れましたが、こういった死殻を うまく細工し 艶まで 出してしまうらしく (苦笑) 場合によっては プロの問屋さんでも 騙されてしまうことがあるそうです。 |
 美しい名前
美しい名前 |
|